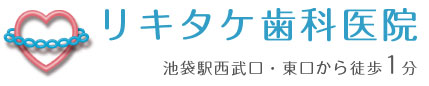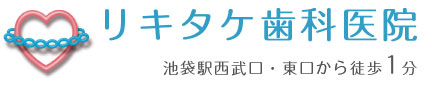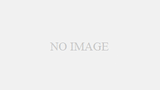第3回 「薬が飲みにくい…」が健康リスクに!?
〜医科・歯科・薬局が連携してできること〜
こんにちは。
前回は、「自宅で受ける歯科医療」と「オーラルフレイル」についてご紹介しました。今回は、高齢者の服薬とお口の健康にまつわる、あまり知られていない重要なテーマに触れたいと思います。
【目次】
1)錠剤を飲み込むのがつらい…そんな声が増えています
2)薬が残ったままだとどうなるの?
3)歯科ができることって?
4)薬局・医科との連携がカギ!
5)まとめ:「口の健康」は薬の効果にも関係します
1)錠剤を飲み込むのがつらい…そんな声が増えています
皆さんは「薬が飲みにくい」と感じたことはありませんか?
高齢になると、
- 舌や喉の動きが鈍くなる
- 口が乾きやすくなる
- 意識がぼんやりして飲み込む力が落ちる
といった理由で、薬が口の中に残ってしまうことがあります。実際に、介護施設では錠剤が口の中に残っていたり、気づかないまま吐き出されているケースも少なくありません。
2)薬が残ったままだとどうなるの?
錠剤がきちんと飲み込めないと、次のようなリスクがあります。
- 薬の効果が出ない(吸収されない)
- 口の中に炎症や潰瘍ができる
- 薬同士が混ざって変色する(黒くなることも)
- 誤って気管に入ると誤嚥や窒息の原因に!
このようなトラブルは、患者さん本人が気づかないことも多いため、身近な人や医療スタッフの「気づき」がとても大切です。
3)歯科ができることって?
歯科では、こうした薬の飲み込みづらさに対してもサポートできます。
- お口の乾燥や汚れをケア**して、残薬を防ぐ
- 義歯の調整**で噛む・飲み込む力を回復
- 飲み込みが難しい方へのリハビリ**(摂食嚥下リハ)
また、「PILL-5」というチェックシートを使えば、どれくらい飲みにくさを感じているかを数値で評価することもできます。
PILL-5[日本語版]アセスメントツール|もしかしたら、錠剤嚥下障害かも | ニュートリー株式会社
4)薬局・医科との連携がカギ!
2024年の診療報酬改定では、医科・歯科・薬局の連携が評価される仕組みもできました。
たとえば…
- 歯科から薬局へ、服薬に関する情報を共有
- 歯科が患者さんの口の状態を医師に報告
- 飲みやすい剤型(ゼリー状や粉薬など)に変更の提案
こうした連携が進めば、\*\*患者さん一人ひとりに合った「安心できる服薬支援」\*\*が実現できるのです。
5)まとめ:「口の健康」は薬の効果にも関係します

お口は、ただ“食べる”ためだけの器官ではありません。
「薬を正しく飲む」「健康を保つ」ための大切な入り口でもあるのです。
- 最近、薬が飲みにくくなった
- 錠剤が喉に引っかかる感じがする
- 口の乾燥が気になる
そんな時は、ぜひ歯科医院にご相談ください。